明けましておめでとうございます。今年もこのblogをどうぞよろしくお願いいたします。2025年最初の記事は、「団塊世代」とその「ジュニア」についてです。
「団塊世代」というのに自分の親は全く当たらないので、「団塊ジュニア」という言葉をずっと他人事(その社会的意味が他人事ということではなく、自分はそれに当てはまらないという意味で)だと思っていたが、2040年にその世代が後期高齢者となるために社会的に大きな問題に直面するだろうということを近頃度々目にするようになり、具体的にどの年代なのだろうと調べてみたら衝撃的だった。1971~1974年に生まれた人達のことだというのだ。私の生年は1972年なので、ど真ん中ではないか。親は「団塊世代」とはおよそ10年ほどずれているのだが当時にしては晩婚だったので、私が生まれたのがちょうど「団塊ジュニア世代」だった、ということだ。なんと遅過ぎる気づきである。
そんな世代なので、我々世代が歩んできた道のりというか、社会的背景が各所で大変良くまとめられている。当たり前だが、全くその通りなのである。なんだか色々なことが懐かしく思い出された。
(参考:団塊ジュニア世代とは?年齢や特徴・消費観、直面する社会課題を徹底解説 )
当の本人の私としては、大きくまとめると「若く多感な時期に劇的で大きな社会変化をいくつも経験してきたのかもしれないな」と感じる。例えばアナログ→デジタル、バブル→バブル崩壊、画一的な教育&単一な人生設計モデル(家族構成や受験戦争、終身雇用制度など)→それらの崩壊&多様化などなど。私も含めそれに馴染めずそこから逸脱した人達にとっては苦労が多くなかなか生きづらい社会だったと思うが、最近は随分楽になった。とすると、逆にその社会に上手く適応できていた人達は適度に意識を変えていないと、もしかすると今が生きづらいのかもしれない。いすれにしても、こうした経験はもちろん無駄ではなく悪い面ばかりでもなく、これらの社会変化の「両方を実体験として知っている」それも「多感で体力があって柔軟な若い時期にそれらを経験している」ということは、大変貴重な財産なのではないかと感じた。単なる「昔はこんな風だった」的な回想や若い頃自慢ではない、その両方を知っているということを、現代以降、どうやって強みにしていくか?という話である。
2040年問題は深刻かもしれないが、圧倒的に人口の多い我々世代が、生きて経験した財産をを社会に還元することをきちんと考えたい。高齢者が社会のお荷物になるようなことばかりが注目される昨今だが、もう少し「1人の人間が生きてきた層の厚み」のようなものに目を向けて、社会の財産として考えても良いのではないかと思うし、そう思ってもらえる老人の1人になりたいと思う。
老人と若者については、以前一度ブログに書いている。
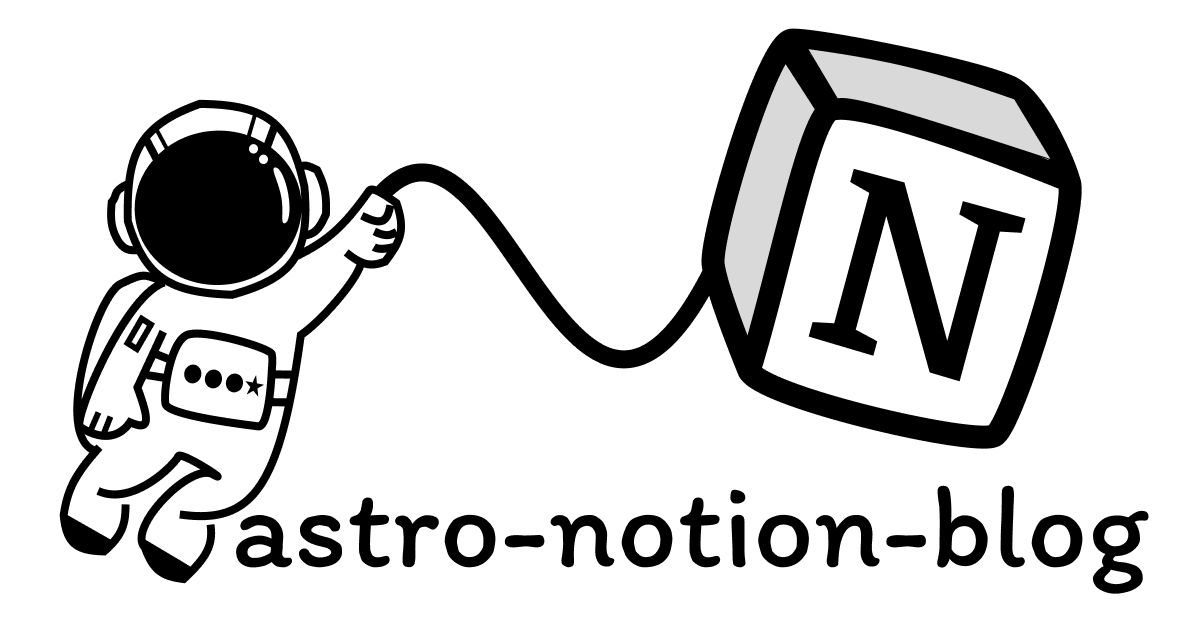
※この記事は書きかけで今後加筆修正される可能性があります。
